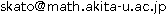|
所属 |
教育文化学部 学校教育課程 初等中等教育講座 初等中等教育コース |
|
生年 |
1987年 |
|
研究室住所 |
秋田県秋田市手形学園町1番1号 |
|
研究室電話 |
018-889-2532 |
|
メールアドレス |
|
加藤 慎一 (カトウ シンイチ)
KATO Shinichi
|
|
|
職務経歴(学内) 【 表示 / 非表示 】
-
2025年04月-継続中
秋田大学 教育文化学部 学校教育課程 初等中等教育講座 初等中等教育コース 講師
-
2020年07月-2025年03月
秋田大学 教育文化学部 学校教育課程 英語・理数教育講座 理数教育コース 講師
職務経歴(学外) 【 表示 / 非表示 】
-
2025年01月-継続中
福島大学 非常勤講師
-
2022年10月-2024年03月
放送大学 非常勤講師(面接授業担当)
-
2020年04月-2020年09月
奈良教育大学 教育学部 非常勤講師
-
2018年04月-2020年06月
奈良佐保短期大学 地域こども学科 講師
-
2013年04月-2018年03月
筑波大学附属聴覚特別支援学校 高等部普通科 教諭
学会(学術団体)・委員会 【 表示 / 非表示 】
-
2010年07月-継続中
日本国
日本数学教育学会
-
2013年06月-継続中
日本国
日本科学教育学会
-
2016年11月-継続中
日本国
日本教育工学会
-
2013年07月-継続中
日本国
日本特殊教育学会
-
2018年04月-継続中
日本国
全国数学教育学会
研究等業績 【 表示 / 非表示 】
-
図形の教材開発における関数の考えへの着目とその意義-集合の概念に基づく関数の考え-
加藤 慎一,森本 明
日本数学教育学会第58回秋期研究大会発表集録 377 - 384 2025年11月 [査読有り]
研究論文(学術雑誌) 国内共著
本稿の目的は,関数の考えを集合の概念に基づいてとらえ直し,それを図形教材の開発における視点として位置づける意義を明らかにすることである.そのために,集合の概念に基づいて関数の考えを定義し,図形教材の開発における視点とする可能性を整理しつつ,具体的な事例を用いて考察を行った.考察を通して明らかになったのは,集合の概念に基づく関数の考えを視点として導入することにより,図形の構成要素の位置や大きさ,要素間の関係や命題などを変数や定数としてとらえる契機が生まれるという点である.このような視点は,生徒が図形を構造的に理解することを促進し,図形教材の開発において有効に機能する可能性が示唆された.
-
数学のよさが分かる高等学校数学科の教材開発:高等学校数学科「三角関数」を事例として
中村 東,加藤 慎一
あきた数学教育学会誌 ( 6 ) 2024年07月 [査読有り]
研究論文(学術雑誌) 国内共著
本稿の目的は,高等学校数学科「三角関数」を事例として,数学のよさが分かる教材を開発すること,そして開発した教材をもとに構想し展開した授業を分析することを通して,その効果を実証的に検討することである.そのために,数学のよさが分かる教材の要件を3つに整理し,それらを満たす教材を開発するための4つの視点を設定した.4つの視点をもとに,教材を開発するとともに,その教材をもとに構想し展開した授業の考察を行った.考察からは,教材開発のための4つの視点が,生徒が社会における数学の有用性や実用性を実感することに寄与することが示唆される.
-
生徒における数学的な態度を涵養する図形教材の開発:「一つのものをほかのものと関係づけてみようとすること」に光をあてて
加藤 慎一,森本 明
東北数学教育学会誌 ( 東北数学教育学会 ) 55 ( 0 ) 16 - 24 2024年03月 [査読有り]
研究論文(学術雑誌) 国内共著
本稿では,特に,数学的な態度のうち,関数の考えの本質である,「一つのものをほかのものと関係づけてみようとする」ことに光をあてて,生徒における数学的な態度を涵養するための教材の要件を明らかにし,その要件を満たす教材を開発することを目的とする。本稿では,「一つのものをほかのものと関係づけてみようとする」ことを涵養する教材の要件として,次の3 つ導出した。第一の要件は,生徒自ら事象から数量や位置,関係,命題を取り出し,それらを対応させたり変化させたりする経験を積むことができることである。第二の要件は,生徒自ら事象から取り出した数量や位置,関係,命題などを対応させたり変化させたりすることにより帰納的,類比的に推論し関係をみいだす経験や,みいだした関係がいつでも成り立つかどうかについて演繹的に推論する経験,発展的・統合的に考察する経験を積むことができることである。第三の要件は,生徒が一つのものをほかのものと関係づけて問題を発見・解決し,その結果として,生徒自ら一つのものをほかのものと関係づけることのよさが分かることが期待されることである。そして,この3 つの要件を満たす中学校第2 学年の生徒を対象にした図形教材を開発した。
-
数学の授業過程における創造的な活動の具現化に関する事例的考察:生徒における数学的な推論に光をあてて
加藤 慎一, 森本 明
東北数学教育学会誌 ( 東北数学教育学会 ) 0 ( 53 ) 53 - 64 2022年03月 [査読有り]
研究論文(学術雑誌) 国内共著
本稿では,数学的な推論,特にPeirceが提唱するリトロダクションが,数学の授業過程における創造的な活動の具現化に,どのような影響をもたらすかについて,高等学校数学科における教材を事例として取り上げ,考察し,その一端を明らかにすることを目的とする。そのために,本稿では,次の2つを観点とする枠組みを導出した;①生徒における数学的概念を覆す,あるいは生徒における予想を覆すような文脈や状況になっているか,②数学的な見方・考え方を発動し,深い学びを創出する契機になることが期待されるか。その上で,高等学校数学科における関数教材を事例として取り上げ,考察を行った。考察からは,次の3つの示唆を得た。①生徒が能動的に問題にかかわり,生徒自ら問いを創出する契機になる,②答えを得ることに終始するのではなく,根拠をもとにしてある事柄や関係が正しいかどうかを説明する契機になる,③数学の授業過程に,領域横断的な学び,あるいは教科横断的な学びを創出する契機になる。
-
数学の授業過程に数学的なプロセスを創出する教師の役割に関する省察:授業における教師の「聞くという行為」に着目して
加藤 慎一, 森本 明
東北数学教育学会誌 ( 東北数学教育学会 ) 0 ( 52 ) 14 - 26 2021年03月 [査読有り]
研究論文(学術雑誌) 国内共著
本研究は,授業前に構想し想定した数学的活動を,教師が授業における教材を介した生徒とのかかわりを通して,生徒の学びの事実に即してリデザインしてその後の授業を展開し,数学的なプロセスを創出する教師の役割について,高等学校数学科の授業を事例として省察する試みである。本稿では,教師における「聞くという行為」が生徒の学びの事実に即した数学的活動のリデザインにどのような影響をもたらしているかについて,その一端を明らかにすることを目的とする。そのために,高等学校の生徒10 名を対象にした高等学校数学科の「図形と方程式」「三角関数」の授業を事例として,教師における「聞くという行為」が生徒の学びの事実に即した数学的活動のリデザインにどのような影響をもたらしているかについて省察した。省察から,教師における「聞くという行為」が,生徒が問題の置かれている文脈と状況にかかわり,それらを既習の数学と結びつけて問題を解決する過程に内在された生徒のアイデアを掘り起こし,その後の授業の展開に顕在化する契機となっていて,それは同時に生徒の学びの事実の新たな一端を教師が発見する契機となっていることが示唆される。その結果として,授業前に構想し想定した数学的活動を,教師は生徒の学びの事実に即してリデザインして授業を展開することで,数学的なプロセスを創出することにかかわっている。
-
「探究的な学び」の実践事例 命題が成り立つ条件について統合的・発展的に考察しよう
加藤 慎一
教育科学/数学教育 ( 明治図書出版株式会社 ) 64 ( 11 ) 60 - 65 2023年10月
総説・解説(商業誌) 単著
本稿では,探究的な学びを重視した中学校数学科における授業デザインの提案を行っている。
-
本実践・研究から見えてくること 数学的に推論することを重視した小学校算数科の授業デザイン
加藤 慎一
秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要第45号 別冊 秋田大学教育文化学部附属小学校令和4年度研究のまとめ 1 - 1 2023年03月
総説・解説(大学・研究所紀要) 単著
附属小学校で実践されたわり算の授業について,「数学的に推論することを重視した算数授業」の視点からまとめた。
-
本実践・研究から見えてくること 統計的探究プロセスを重視した中学校数学科の授業デザイン
加藤 慎一
秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要第45号別冊 附属中学校令和4年度研究報告 ( 90 ) 156 - 156 2023年03月
総説・解説(大学・研究所紀要) 単著
附属中学校で実践された「データの活用」領域の授業について,「統計的探究プロセスを重視した数学授業」の視点からまとめた。
-
本実践・研究から見えてくること 認知的葛藤を誘発する算数授業
加藤慎一
秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要第44号 別冊 秋田大学教育文化学部附属小学校令和3年度研究のまとめ 1 - 1 2022年03月
総説・解説(大学・研究所紀要) 単著
附属小学校で実践されたわり算の授業について,「認知的葛藤を誘発する算数授業」の視点からまとめた。
-
本実践・研究から見えてくること 関数的な見方・考え方を働かせて図形の性質の理解を広げ深める数学授業
加藤慎一
秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要第44号別冊 附属中学校令和3年度研究報告 ( 89 ) 151 - 151 2022年03月
総説・解説(大学・研究所紀要) 単著
附属中学校で実践された「図形」領域の授業について,「関数的な見方・考え方を働かせて図形の性質の理解を広げ深める数学授業」の視点からまとめた。
-
Kato S.
Proceedings of the Asian Technology Conference in Mathematics ( Mathematics and Technology, LLC ) 366 - 375 2021年12月 [査読有り]
研究論文(国際会議プロシーディングス) 単著
The purpose of this study was to develop teaching materials for 6th-grade elementary school students in Japan, focusing on retroductive inference, to develop their statistical thinking and explain its use. Recently, MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) has made “Programming Education” compulsory at elementary schools in Japan. The purpose of “Programming Education” in Japan is to develop the programming thinking of students based on their computational thinking and enhance their academic ability in teaching and learning a particular subject, rather than learn coding. However, few studies have been conducted on the development of programming thinking based on computational thinking, for enhancing the academic ability of students. “Retroduction” is effective in promoting computational thinking. Also, the development of mathematical and computational thinking is interacted by one another. Therefore, we developed a teaching material to enable the students to engage in retroductive inference. A context and situation setting were provided to them to make retroductive inferences. The results indicated that it seems reasonable to assume that the teaching material promoted their computational thinking and developed their statistical thinking by creating phases for retroductive inferences.
-
関数の考えを視点とした「図形」領域の指導の改善に向けた基礎的検討:全国学力・学習状況調査(小学校算数)の「図形」領域の問題分析をもとに
加藤 慎一,小原 舞音,森本 明
福島大学教職実践研究 ( 4 ) 217 - 231 2025年03月
研究論文(大学,研究機関紀要) 国内共著
本稿の目的は,小学校算数科の「図形」領域において,児童が直面する困難な状況の一端を具体的にとらえ,その克服に向け,充実すべき数学的活動の設計とその提案を行うこと,にある。そのために,関数の考えを視点として,全国学力・学習状況調査(小学校算数)の「図形」領域の問題分析をもとに,その困難な状況の克服に向け,充実すべき数学的活動についての考察を行った。分析と考察を通して,小学校算数科の「図形」領域における関数を視点とした操作活動の設計とその提案ができた。
-
聞くという行為にみる教師の意思決定の基となる数学的な態度の基礎的検討:数学教師をめざす大学生を対象にしたインタビュー調査をもとに
加藤 慎一,小原 舞音,森本 明
福島大学教職実践研究 ( 3 ) 17 - 32 2024年03月
研究論文(大学,研究機関紀要) 国内共著
本稿の目的は,聞くという行為に,教師の意思決定の基となる数学的な態度を,数学教師をめざす大学生を対象にしたインタビュー調査をもとに,片桐(1988)の枠組みからとらえ,その様相を検討すること,併せて,数学的な態度をとらえる枠組みの妥当性を検討すること,である。検討を通して,聞くという行為に教師の意思決定の基となる数学的な態度の様相の一端をつかまえた過程,ならびに枠組みの妥当性を裏付けた過程,を報告する。
-
算数授業過程の子どもにおける式の見方の様相とその変容に関する事例的考察
森本 明,小原 舞音,東城 恵,菅野 雄大,加藤 慎一
白鷗大学教育学部論集 17 ( 2 ) 101 - 120 2023年11月
研究論文(大学,研究機関紀要) 国内共著
本稿は,算数授業過程を,自立的ときに協働的,数学的に問題発見・解決する過程としてとらえ,その過程のうち,式表現を吟味する子どもの取り組みに光をあて,算数の学習過程の充実と授業改善に向けて考察する一研究である。本稿の目的は,「子どもが式表現を吟味する自立的ときに協働的な取り組みに光をあて,①子どもの自立的な取り組みにおいて子どもに発動される式の見方にどのような様相があるのか,また②異なる式の見方をする子どもどうしが協働に向けて式表現を吟味しあう取り組みにはどのような様相があるのか」という研究の問いにこたえることである。
-
関数の考えを活用した統合的・発展的に考察する力の評価ー数学科教員をめざす大学生を対象としてー
加藤 慎一,江森 英世,森本 明
大谷大学教職支援センター研究紀要 ( 16 ) 39 - 56 2023年09月
研究論文(大学,研究機関紀要) 国内共著
本稿の目的は,統合的・発展的な考察の促進に重要な役割を果たす関数の考え(中島, 1981)に光をあてて,加藤・江森・森本(2022)で検討した調査問題および評価枠組みをもとに,教員をめざす大学生が関数の考えを活用した統合的・発展的に考察することに,どのような課題を抱えているかについて明らかにすることである。本稿では,加藤・江森・森本(2022)によって提案した評価枠組みを用いて,教員をめざす大学生における関数の考えを活用した統合的・発展的に考察する力の評価を行った。各学生の記述を分析・評価し,個々人が抱える課題の一端を明らかにしたことが本稿の成果である。
-
数学的モデル化過程を重視した数学授業の考察:高等学校数学科「三角関数」を事例として
中村 東,加藤 慎一
秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要 ( 45 ) 63 - 70 2023年03月 [査読有り]
研究論文(大学,研究機関紀要) 国内共著
本稿では,数学的モデル化過程を重視した高等学校数学科の授業において,生徒が数学的モデル化過程をどのように遂行しているか,その様相を実証的に明らかにすることを目的とする。そのために,数学的モデル化過程を重視した三角関数の授業を構想・展開し,授業において生徒が遂行した数学的モデル化過程を考察した。考察からは,現実事象を定式化して数学的モデルを作成し,その作成した数学的モデルから数学的結論を導き出して,その数学的結論を現実事象に照らして解釈・評価・比較する過程を繰り返し,数学的モデルの改良を求めて,数学的モデル化過程を繰り返すスパイラル的に発展する様相をみいだすことができた。その際,数学的モデル化の段階を逆行あるいは往復をしたり,飛躍したりしてよりよりモデル化を図ろうとしていることが示唆される。
-
小学校算数科における児童の遡及的推論を重視したプログラミング教育の意義
加藤 慎一
日本科学教育学会研究会研究報告 ( 一般社団法人 日本科学教育学会 ) 35 ( 3 ) 109 - 112 2020年12月
研究論文(研究会,シンポジウム資料等) 単著
<p>2020年度から小学校において,プログラミング教育が必修化されている.プログラミング教育のねらいを達成するために,各教科等において,プログラミング教育の系統的かつ効果的な実践に向けて教材を開発することおよびカリキュラム・マネジメントを推進することが求められている.しかしながら,小学校算数科において,まだまだ十分な検討がなされているとは言いがたい.そこで,本研究では,Peirceの遡及的推論(retroductive inference)に光をあてて,小学校算数科におけるプログラミング教育の系統的かつ効果的な実践に向けた教材を開発することを目的とする.本稿では,小学校算数科の「正多角形の作図」の授業を例に,小学校算数科のプログラミング教育において,児童の遡及的推論を重視することの意義にふれることを目的とする.</p>
-
関数的な見方・考え方のよさが分かる活動デザインの探究過程~教師をめざす学生の探究過程における思考の反覆に光をあてて~
加藤 慎一,森本 明
日本科学教育学会年会論文集 ( 43 ) 636 - 639 2019年08月
研究論文(研究会,シンポジウム資料等) 国内共著
数学的な見方・考え方のよさが分かる授業を具現することは,児童生徒における数学的に考える資質・能力を高める上で重要である。算数数学科の教科の特性を考慮しつつ,一人一人の児童生徒の学力・学習状況に応じながら,数学的に考える資質・能力を高めるために,数学的な見方・考え方のよさが分かる教材と授業づくりにおいて不断の検証改善を重ねる構えを身につけることは,教師をめざす学生にとって必要だろう。また,その中で,具体的に活動デザインを探究すること,そしてそれを経験とすることを学生のうちに積んでおくこともまた必要だろう。本研究は,このように考える立場から,思考の反覆に光をあてて,学生が数学的な見方・考え方のよさが分かる活動デザインを探究する過程を考察する。本稿では,関数的な見方・考え方に焦点化して,そのよさが分かる活動デザインの学生による探究過程を促進することを,これまでの成果ならびに課題の一端を報告する。
-
教師をめざす学生における 算数科授業づくりの探究過程への支援とその試み~思考の反覆による短期大学生における数学的活動の充実を図る試み~
加藤 慎一,森本 明
日本科学教育学会年会論文集 ( 42 ) 589 - 592 2018年08月
研究論文(研究会,シンポジウム資料等) 国内共著
教師をめざす学生が,算数科授業づくりの探究過程に興味・関心をもち,そのうえで授業づくり探究の基礎的・基本的な資質・能力を身に付けることは,これからの算数・数学教育の充実と発展,とりわけ教師における教材と授業づくりの専門性の継承,において必要かつ重要な課題である。本研究は,このように考える立場から,教師をめざす学生における思考の反覆による算数科授業づくりの具現化を図る試みである。本稿では,研究経過ならびに成果と課題の一端を報告する。
-
統合的・発展的な考察を重視した授業デザイン:中学校第1学年「図形の位置関係」の学習をもとに
山崎 洋,加藤 慎一
日本数学教育学会第107回大会発表要旨集(石川大会) 246 - 246 2025年08月
研究発表要旨(全国大会,その他学術会議) 国内共著
-
聴覚特別支援学校の数学の授業過程の構成と展開における教師の数学的な態度に関する基礎的検討−教師における聞くという行為にみる意思決定に光をあてて−
加藤 慎一,森本 明,小原 舞音,東城 恵,米山 文雄
ろう教育科学 66 ( 2 ) 26 - 28 2025年01月
速報,短報,研究ノート等(学術雑誌) 国内共著
-
算数・数学の授業過程における個別最適な学びと協働的な学びの往還について考える
加藤 慎一
AKITA算数・数学通信 ( 教育出版株式会社 ) 3 - 4 2024年05月
その他記事 単著
本稿では,算数・数学の授業過程において,個別最適な学びと協働的な学びを一体的にとらえることの必要性と重要性について明らかにしている。
-
個別最適な学びを実現する算数・数学の授業デザインについて考える
加藤 慎一
AKITA算数・数学通信 ( 教育出版株式会社 ) 3 - 4 2024年02月
その他記事 単著
本稿では,個別最適な学びを実現する算数・数学の授業デザインにおける教師の役割について明らかにしている。
-
聴覚特別支援学校の数学の授業過程へのICT活用の状況と課題
森本 明,加藤 慎一,東城 恵,小原 舞音,米山 文雄
ろう教育科学 65 ( 2 ) 56 - 58 2024年01月
速報,短報,研究ノート等(学術雑誌) 国内共著
◆原著論文【 表示 / 非表示 】
◆総説・解説【 表示 / 非表示 】
◆国際会議プロシーディングス【 表示 / 非表示 】
◆⼤学,研究機関紀要【 表示 / 非表示 】
◆研究会,シンポジウム資料等【 表示 / 非表示 】
◆その他【 表示 / 非表示 】
Book(書籍) 【 表示 / 非表示 】
-
聴覚障害教育の基本と実際
長南 浩人,澤 隆史,佐藤 正幸,佐々木 順二,藤本 裕人,仲原 美奈子,加藤 哲則,黒田 生子,小渕 千絵,岡野 由実,大鹿 綾,増田 早哉子,富永 崇仁,坂口 嘉菜,手塚 清,渡部 杏菜,橋本 時浩,奥沢 忍,高井 小織,数馬 梨恵子,加藤 慎一,小林 雅樹,廣瀬 由美,田中 豊大,内田 匡輔,守屋 誠太郎,螧原 けい子,須田 美喜子,山本 晃 ( 担当: 単著 )
田研出版株式会社 2025年09月 ISBN: 978-4-86089-054-4
学術書
-
「生徒が主語の学び」を実現する中学校数学科新発問パターン集
玉置 崇,有金 大輔,和田 勇樹,菅原 大,原田 壮一,力久 晃一,菅野 恵悟,武藤 寿彰,大友 正純,稲熊 紀昭,立花 佳帆,佐賀井 隼人,新井 健使,近藤 俊男,鈴木 克希,堀 孝浩,加藤 慎一,柴田 翔,銀杏 祐三,山崎 浩二,井上 芳文,吉村 昇 ( 担当: 単著 )
明治図書出版株式会社 2025年07月 ISBN: 978-4-18-372929-3
学術書
-
聴覚障害児の学習と指導-発達と心理学的基礎-
四日市 章,鄭仁 豪,澤 隆史,ハリー・クノールス,マーク・マーシャーク,今泉 敏,佐藤 正幸,斎藤 友介,三枝 里江,館山 千絵,庄司 和史,松本 末男,相澤 宏充,武居 渡,霍間 郁実,松藤 みどり,左藤 敦子,村瀬 忍,小渕 千絵,林田 真志,有海 順子,白澤 麻弓,能美 由希子,甲斐 更紗,長南 浩人,田原 敬,大澤 瑞穂,前川 久樹,金 恩河,濱田 豊彦,喜屋武 睦,茂木 成友,大部 令絵,中山 哲志,新海 晃,雁丸 新一,田中 耕司,深江 健司,加藤 慎一,脇中 起余子,黒田 健次,爲川 雄二,金子 俊明,杉山 梓,有馬 里佐,原田 公人 ( 担当: 単著 )
株式会社明石書店 2018年09月 ISBN: 978-4-7503-4730-1
学術書
本章では,言語獲得の遅れが,聴覚障害児の教科学習と指導,とりわけ算数・数学教育における学習指導において,どのような影響を与えているかについて書かれている英文を翻訳し,それに加筆・修正したものである。日本での聴覚障害児を対象とする算数・数学教育に関する研究と比較し,聴覚障害児のための算数・数学教育の今後の課題を明らかにしている。
-
聴覚障害生徒の力を育むために-筑波大学附属聴覚特別支援学校(聾学校)高等部の実践-
橋本 時浩,武林 靖浩,鈴木 淳一,雁丸 新一,竹村 茂,青柳 泰生,秋島 康範,荒川 修,内野 智仁,榎並 裕子,岡本 三郎,加藤 慎一,久川 浩太郎,小林 早由利,最首 一郎,地紙 かおる,鈴木 初美,鈴木 牧子,高木 智史,玉生 美智子,田万 幸子,棚原 千衣,外山 菜保子,長島 素子,苦瓜 道代,松本 邦子,横山 知弘,芳之 内修,油井 淳 ( 担当: 共著 )
聾教育研究会 2014年03月
その他
科研費(文科省・学振)獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
教師における数学的な態度を涵養する教員養成と教員研修の一体的なプログラムの開発
基盤研究(C)
研究期間: 2024年04月 - 2027年03月 代表者: 加藤 慎一
-
小学校算数科におけるプログラミング教育の系統的かつ効果的実践に向けた教材開発
若手研究
研究期間: 2019年04月 - 2022年03月 代表者: 加藤 慎一
2020年から小学校においてプログラミング教育が必修化され,各教科でプログラミング教育の充実を図ることが求められている。これまでも小学校算数科におけるプログラミング教育に関する研究はなされているものの,確立したカリキュラムを構築するための十分な検討はなされていない。そこで,本研究では,プログラミング教育のカリキュラムを開発するための基礎的研究として,小学校算数科におけるプログラミング教育の系統的かつ効果的実践に向けた教材を開発し,その有効性を検討することを目的とする。
-
対話を通して問いを創出し追究する聴覚障がい児の数学授業におけるICT活用の可能性
奨励研究
研究期間: 2017年04月 - 2018年03月
その他競争的資金獲得実績 【 表示 / 非表示 】
-
学校数学カリキュラムに内在するデータサイエンス教育の特定
提供機関: 公益財団法人かんぽ財団 令和7年度調査研究助成
研究期間: 2025年07月 - 2026年06月 代表者: 加藤 慎一
資金支給機関区分:その他
-
秋田県における算数の学びのコミュニティ創出事業
提供機関: 秋田大学 秋田大学令和6年度計画推進経費
研究期間: 2024年08月 - 2025年03月 代表者: 加藤慎一
資金支給機関区分:その他
本事業では,その学びの変革に対応するために,地域での算数講座の実施を通して,学びのコミュニティを創出し,子どもたちが多様な他者と協働しながら問題発見・解決することのよさやたのしさを実感できるようにすること,そしてその算数講座の運営に学生が関わることによって,学生の確かな実践力を育成することを目指す。小学生を対象に,多様な他者と協働しながら実社会や日常生活における問題発見・解決する算数講座を実施する。
-
児童生徒における数学的な態度を涵養する教材の開発
提供機関: 秋田大学 令和5年度秋田大学若手研究者支援事業
研究期間: 2023年08月 - 2024年03月 代表者: 加藤 慎一
資金支給機関区分:その他
本研究では,児童生徒における数学的な態度を涵養する教材を開発することを目的とする。その目的を達成するために,次の3つの下位目標を掲げ,行動計画とする。
(1)児童生徒における数学的な態度を涵養する教材の要件を抽出する。
(2)算数・数学の教科書および授業の分析により,(1)で抽出した要件を満たすICT教材案を作成する。
(3)ICT教材を用いた授業実践に向けて予備実験を行い,開発したICT教材を量的かつ質的に評価する。 -
秋田県における算数の学びのコミュニティ創出事業
提供機関: 秋田大学 秋田大学令和5年度計画推進経費
研究期間: 2023年08月 - 2024年03月 代表者: 加藤慎一
資金支給機関区分:その他
本事業では,その学びの変革に対応するために,地域での算数講座の実施を通して,学びのコミュニティを創出し,子どもたちが多様な他者と協働しながら問題発見・解決することのよさやたのしさを実感できるようにすること,そしてその算数講座の運営に学生が関わることによって,学生の確かな実践力を育成することを目指す。小学生を対象に,多様な他者と協働しながら実社会や日常生活における問題発見・解決する算数講座を実施する。
-
個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図るオンライン教育システムの構築
提供機関: 秋田大学 令和4年度秋田大学研究プロジェクト強化支援事業
研究期間: 2022年11月 - 2025年03月 代表者: 加藤慎一
資金支給機関区分:その他
Society5.0の時代に向けて,日本の学校教育は学びの変革が求められている。秋田県においても2021年度からのGIGAスクール構想の実施,秋田県が抱える教育の環境的要因に加え,コロナ禍であることもあいまって,学校教育におけるICTの効果的な活用について検討することが喫緊の課題となっている。本研究プロジェクトでは,この課題の解決を図り,秋田県の教育のさらなる充実を図ることを目的としている。本研究プロジェクトでは,特に次代を切り拓く児童生徒の資質・能力をはぐくむために必要かつ重要な視点である,個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実を図るためのオンライン教育システムの構築を目指す。
受託事業受入実績 【 表示 / 非表示 】
-
教員研修高度化支援 教員研修の高度化に資するモデル開発事業「地域・学校の壁を越える新時代の授業研究システムの構築」
提供機関: 文部科学省
契約期間: 2023年05月 - 2024年03月 代表者: 後藤猛
学会等発表 【 表示 / 非表示 】
-
図形の教材開発における関数の考えへの着目とその意義-集合の概念に基づく関数の考え-
加藤 慎一,森本 明
日本数学教育学会第58回秋期研究大会 2025年11月 - 2025年11月
-
小・中学校の教職員における特別支援教育の専門的な知見や経験等を学ぶことへの意識とその具体的な取り組みの様相
森本 明,小原 舞音,加藤 慎一,東城 恵
日本特殊教育学会第63回大会 2025年09月 - 2025年09月
-
統合的・発展的な考察を重視した授業デザイン:中学校第1学年「図形の位置関係」の学習をもとに
山崎 洋,加藤 慎一
日本数学教育学会第107回全国算数・数学教育研究(石川)大会 2025年08月 - 2025年08月
-
関数概念の理解を促進するICT活用について考える
加藤 慎一,中澤 房紀 [招待有り]
The 26th T^3 Japan Annual Meeting 2025年08月 - 2025年08月
-
統合的・発展的な考察を重視した「図形」領域の単元構成について考える:中学校第2学年「図形」領域に焦点をあてて
山崎 洋,加藤 慎一
あきた数学教育学会第8回定例研究会 2025年07月 - 2025年07月
職務上の実績に関する事項 【 表示 / 非表示 】
-
2016年04月-2018年03月
筑波大学附属学校教育局プロジェクト研究2(学校教育におけるICT活用に関する研究2)研究員
-
2014年04月-2016年03月
筑波大学附属学校教育局プロジェクト研究2(学校教育におけるICT活用に関する研究)研究員
担当授業科目(学内) 【 表示 / 非表示 】
-
2023年04月-継続中
初年次ゼミ「学校教育課程理数教育コース」
-
2021年04月-継続中
小・中・高連携の教科教育カリキュラム開発Ⅰ
-
2021年04月-継続中
数学科ICT活用教育
-
2021年04月-継続中
秋田型アクティブラーニングの授業デザインと評価
-
2021年04月-継続中
教科教育実践の理論と展開
学内活動 【 表示 / 非表示 】
-
2025年04月-継続中教育実習実施委員会委員 (所属部局内委員会)
-
2025年04月-継続中教職入門実施委員会委員 (所属部局内委員会)
-
2025年04月-継続中キャリア委員会副委員長 (所属部局内委員会)
-
2024年04月-継続中学術研究推進会議委員 (所属部局内委員会)
-
2023年02月-2024年02月秋田大学教育文化学部・附属学校学部共同委員会中学校部会部会長 (所属部局内委員会)
学会・委員会等活動 【 表示 / 非表示 】
-
秋田県算数・数学教育研究会
2025年11月秋田県算数・数学教育研究会研究部「ICTを活用した小学校算数科の授業研究会」開催
-
秋田県算数・数学教育研究会
2025年11月秋田県算数・数学教育研究会研究部「ICTを活用した高等学校数学科の授業研究会」開催
-
日本数学教育学会
2025年11月第58回秋季研究大会における座長
-
あきた数学教育学会
2025年08月-継続中会長
-
秋田県検証改善委員会
2025年07月-継続中委員
学外の社会活動(高大・地域連携等) 【 表示 / 非表示 】
-
秋田大学教育文化学部附属小学校「令和7年度公開研究協議会Ⅱ」
2025年12月秋田大学教育文化学部附属小学校の令和7年度公開研究協議会Ⅱにおいて,研究協力者として指導助言を行った。
-
秋田大学教育文化学部附属小学校「令和7年度公開研究協議会Ⅱ・事前授業検討会(第1学年・ながさくらべ)」
2025年12月秋田大学教育文化学部附属小学校の令和7年度公開研究協議会Ⅱの事前授業検討会において,研究協力者として指導助言を行った。
-
秋田市立築山小学校・第2回校内授業研究会(算数科)における指導・助言
2025年11月秋田市立築山小学校・第2回校内授業研究会(算数科)において,第4学年の複合図形の面積に関する授業を参観し,指導助言を行った。
-
秋田市教育委員会指導主事等学校訪問計画「中学校数学科第2学年・平行と合同」
2025年11月秋田市教育委員会指導主事等学校訪問計画の教科指導委員として,中学校数学科第2学年の平行と合同の授業を参観し,指導助言を行った。
-
秋田市教育委員会指導主事等学校訪問計画「小学校算数科第2学年・長いものの長さ」
2025年11月秋田市教育委員会指導主事等学校訪問計画の教科指導委員として,小学校算数科第2学年の長いものの長さに関する授業を参観し,指導助言を行った。
メディア報道 【 表示 / 非表示 】
-
県内の特別支援校、ICT活用で学びやすく 障害の程度や特性に応じて授業
2023年02月27日
株式会社秋田魁新報社
-
遠隔授業をどう効果的に
2021年08月20日
株式会社北鹿新聞社
-
算数を楽しく学ぼう
2019年08月
株式会社奈良新聞社